どちらが得?あなたの老後プラン次第です
「年金を早くもらうか、遅くもらうか」――
これは、老後の生活設計を考えるうえでとても重要なテーマです。
この記事では、年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給の違いと注意点をわかりやすく解説します。
① 繰り上げ受給とは?
通常、年金は65歳から受け取りが始まりますが、
最大5年前の60歳から受給を開始できる制度があります。
これが「繰り上げ受給」です。
💡 メリット
- 早くもらえるため、生活費の足しになる
- 働けない・無収入の期間をカバーできる
- 受給開始後すぐに現金が入るため安心感がある
⚠️ デメリット
- 一度繰り上げると一生減額されたまま
- 減額率は1か月ごとに0.4%(5年早めると24%減)
- 長生きした場合、生涯でもらえる総額が少なくなる
📉 具体例
65歳で受給:月10万円
60歳で繰り上げ:月7万6,000円(24%減)
85歳まで生きた場合の総受給額は、
- 65歳開始 → 約2,400万円
- 60歳開始 → 約2,280万円
つまり、早くもらっても長生きすると損になる可能性があります。
② 繰り下げ受給とは?
逆に、65歳以降に受給開始を遅らせることを「繰り下げ受給」といいます。
現在は75歳まで繰り下げ可能です。
💡 メリット
- 1か月遅らせるごとに0.7%増(最大84%アップ!)
- 長生きするほど総受給額が増える
- 生活に余裕がある人に向く
⚠️ デメリット
- 受給開始まで無収入期間が長くなる
- その間の生活費を「自分の貯蓄」で補う必要あり
- 早く亡くなった場合、受け取れる額が少なくなる
📈 具体例
65歳で受給:月10万円
75歳で繰り下げ:月18万4,000円(+84%)
85歳まで生きた場合の総受給額は、
- 65歳開始 → 約2,400万円
- 75歳開始 → 約2,208万円
70代後半から長生きすればするほど“お得”になります。
③ どちらを選ぶべき?判断のポイント
| タイプ | 向いている受給方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 早期退職・貯金が少ない | 繰り上げ受給 | 生活費の確保を優先 |
| 長生き家系・健康に自信あり | 繰り下げ受給 | 将来の受取額を重視 |
| 貯蓄に余裕がある | 繰り下げ+資産運用 | 年金を増やしつつ運用益を得る |
| 公的年金以外の収入がある | 繰り下げ受給 | 受給開始を遅らせやすい |
④ どん☆流アドバイス:「生涯現役」のマインドを持とう
年金をいつからもらうか――それも大切ですが、
もっと重要なのは「老後も収入を得られる力」を持つことです。
もし資産が少ないなら、
「引退」ではなく「働き方を変える」
という選択もあります。
たとえば、
- 週3日のパート
- 自宅でできる副業
- 好きなことを小さく仕事にする
月に5万円でも10万円でも収入があるだけで、
生活の安心感はまったく違います。
⑤ 年金+働く+運用で“安心3本柱”をつくる
老後のお金の不安をなくすには、
「年金+労働収入+資産運用」の3本柱を意識しましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 年金 | 公的な最低限の収入源。受給タイミングを計画的に。 |
| 労働収入 | 働けるうちは続けて“現役マインド”を保つ。 |
| 資産運用 | NISAなどで運用益を育てて将来の余裕資金に。 |
どれか一つでは不安定でも、
三本柱で支えれば、老後資金の土台は強固になります。
🧭 まとめ:年金は「もらい方」で人生が変わる
- 繰り上げ受給は“今の生活重視”
- 繰り下げ受給は“将来の安心重視”
- 自分の健康・貯蓄・働き方に合わせて選ぶ
- 生涯現役の気持ちが老後の不安を減らす
年金は「もらう」ものではなく、「設計する」もの。
未来の自分を守るために、今から準備を始めましょう。

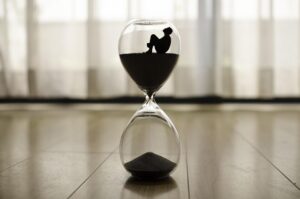
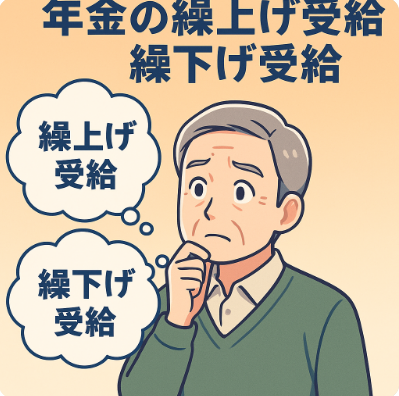







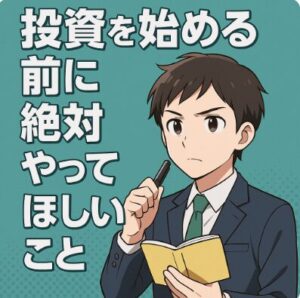
コメント