日本の労働組合の中央組織「連合(日本労働組合総連合会)」は、
2025年の春闘(しゅんとう)では、「5%以上の賃上げ」を目指す方針を打ち出していました。
“賃金上昇が当たり前になる時代”が少しずつ見えてきたとも言えますが、来年の春闘は、「特に中小企業において、6%以上の賃上げ要求」を掲げる予定とのことです。
春闘(しゅんとう)とは?
「春闘」とは、春に行われる労働組合と企業の賃金交渉のことです。
毎年2〜3月ごろに、連合を中心とした各労働組合が、
企業側と「どれくらい給料を上げるか」を話し合います。
つまり、春闘の結果がその年の日本全体の賃金動向を左右するのです。
来春闘の焦点:引き続き5%の賃上げは実現するのか?
連合の方針では、
- 大企業:5%以上の賃上げを目標
- 中小企業:6%以上の賃上げを要請
という形で、より中小企業の底上げを重視しています。
ただし、ここでポイントとなるのは「実質賃金」です。
名目賃金が上がっても、物価が上がれば実質賃金はマイナス。
現在、日本ではエネルギー価格・食品価格の上昇などが続いており、
物価上昇率は依然として2〜3%台で推移。
そのため、名目賃金が上がっても生活実感はなかなか改善されていないのが現状です。
実質賃金がマイナス基調のままな理由
① 物価上昇が想定以上に続いている
特に食料・光熱費・住宅関連の値上げが家計を直撃しています。
② 中小企業の賃上げ余力が限られている
中小企業では人件費を上げたくても、
取引価格や販売価格に反映できず、苦しい経営を強いられているケースが多いです。
③ 一時金・ボーナスで支える企業が多い
ベースアップ(基本給の底上げ)ではなく、
一時的な手当や賞与で対応している企業も少なくありません。
それでも「賃上げの流れ」は続いている
とはいえ、ここ数年で日本の賃金交渉の流れは明らかに変わってきています。
- 2023年:平均賃上げ率3.6%(約30年ぶりの高水準)
- 2024年:平均賃上げ率5.2%(33年ぶりの伸び)
そして、2025年の平均賃上げ率は5.25%の賃上げ をする動きとなっています。
これは、長年続いた「賃金が上がらない日本」から、
少しずつ脱却しようとしているサインともいえます。
賃上げが続けば、経済の好循環も期待できる
賃上げが実現すれば、
労働者の可処分所得が増え、消費が活発化します。
消費が増えれば企業の売上が上がり、さらに賃金に還元できる――
この「賃金 → 消費 → 成長 → 再び賃金」の好循環が生まれます。
日本経済が本格的に成長モードに入るには、
この流れをいかに持続させるかが重要です。
今後の課題:中小企業への波及と物価対策
課題は、中小企業への波及です。
日本の雇用の約7割は中小企業が支えています。
そのため、中小企業でもしっかり賃上げができる仕組み作りが必要です。
また、同時に物価の安定も欠かせません。
賃金が上がっても物価がさらに上がってしまえば、実質的な生活改善にはつながりません。
まとめ:賃上げムードは日本経済の追い風
- 2025年春闘では、連合が賃上げ率5%以上を要求・達成
- 中小企業は6%以上を目標
- 実質賃金は依然マイナスだが、流れは確実に変わりつつある
- 賃上げが広がれば、経済の好循環が生まれる
日本全体が「給料が上がる時代」に変わるには、
企業も、国も、そして私たち一人ひとりの意識の転換が必要です。
物価に負けない賃上げが続けば、きっと景気も、人の気持ちも明るくなる。
これからの日本経済に、少しずつ希望の光が見えてきました。
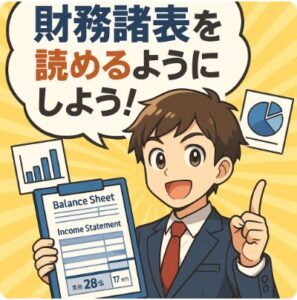




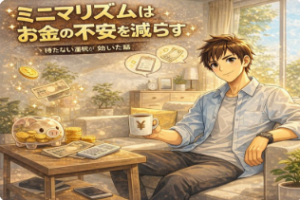

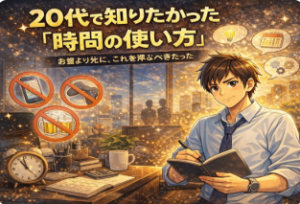

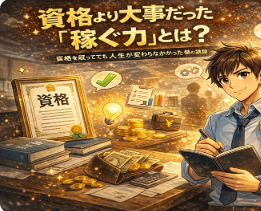
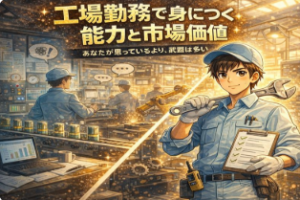
コメント