1. 世界的に見ても“金融リテラシーの低さ”が課題
OECD/INFEの調査によると、最低限の金融知識(例えば単利・複利、リスク分散の理解など)を持つ成人は世界全体で約56%程度。ただしOECD諸国平均では約63%とやや高めです。
 どん☆
どん☆※OECD/INFEとは、経済協力開発機構(OECD)が2008年に設立した「金融教育に関する国際ネットワーク(International Network on Financial Education)」の略称です。金融教育に関する情報共有や分析を行い、加盟国における金融教育の推進を目的としています。
一方、日本では複利に関する理解者がわずか37%に留まっており、住宅ローン保有者でも理解率は50%前後という低水準です。
さらに2022年の調査では、インフレの意味を理解している人は84%と高いものの、「お金の時間価値」は63%、「複利」の理解は42%と低く、多くの人が重要な金融概念に理解が追いついていません。
2. 金融の話題は“家庭でも公の場でも”タブー化しがち
日本ではお金の話、特に投資や家計の管理を家庭で話題にすることが少なく、社会的にもタブー視されている傾向があります。
その結果、学校教育の中でも、お金に関する体系的な学びの機会はほとんどなく、親世代の会話の影響も小さいため、金融リテラシー向上の土壌が整っていません。
その一方で、PISA(国際学力調査)では、家庭で「お金のことを話す家庭の子ども」は金融リテラシーが高い傾向にあるというデータもあり、やはり日常的な会話・教育の重要性が浮き彫りになっています。
なぜお金の勉強をしてこなかったのか?その原因とは
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 学校で教えてこなかった | 教育カリキュラムに金融教育がほとんどない |
| 家庭でも話題にされない | 親世代も金融の話に不慣れで、コミュニケーションが不足 |
| 難しそうに見える | 難解なイメージから、学びのハードルが高いと感じられている |
| タブーや恥ずかしさ | 「恵まれていない」と思われたくない心理による抵抗感 |
日本の金融リテラシーを向上させるためにできること
- 家庭でお金の話をしよう
「お小遣いの貯め方」や「どうして貯金するのか」など、簡単な話題からOK。 - 学習を身近に
インフレ、複利、リスク分散などの理論を、日々の生活の中で例に挙げて説明する。 - 学校・SNS・ブログで啓発活動
家庭やメディアを通じた気軽な学びの場作りが鍵。 - 大人の学び直しを推進
社会人向けの金融講座や動画教材、自治体の支援講座を活用しよう。
まとめ
- 日本の金融リテラシーは、欧米や先進国と比べて明らかに低い水準にあります。
- 学校や家庭で金融教育が欠如していることが原因の一つ。
- しかし、「学び直し」や「家庭での会話」を通じて、誰でも金融力を高めることは可能です。
生活に必須なお金の知識だからこそ、これからもっとみんなで学びを広げていきたい。
あなたの周りで、ちょっとしたお金の話題をシェアできる人が増えたら、日本の未来はもっと豊かになります。







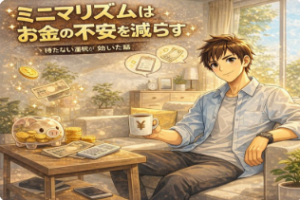

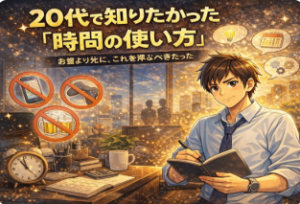

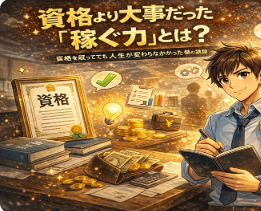
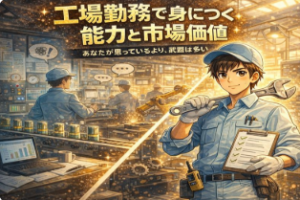
コメント